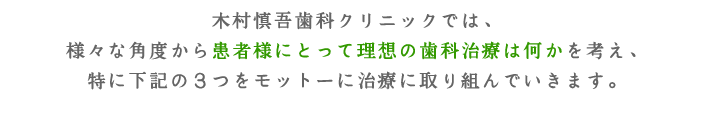


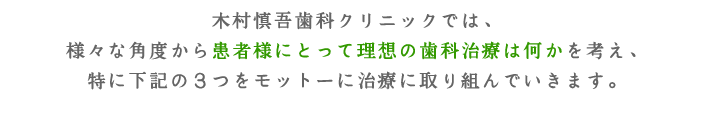


1989年
岡山大学歯学部卒業
1989年4月~1990年3月
名古屋大学口腔外科入局
1990年4月~1991年3月
中部労災病院口腔外科勤務
1991年4月~1995年3月
掛川市民病院口腔外科勤務
1995年4月~1997年6月
名古屋市中区の開業医にて勤務
1997年7月~
木村慎吾歯科クリニック開業

| 埋伏歯抜歯(親知らず) | 1,000例以上 |
|---|---|
| 歯根嚢胞摘出術 | 500例以上 |
| 顎骨骨折整復術 | 50例以上 |
| 上顎洞根治術 | 20例以上 |
| 唾石摘出術 | 10例以上 |
| 骨切り術(外科矯正) | 5例以上 |
| インプラント | 300例以上 |

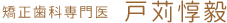
26年間にわたり臨床・研究・教育に従事し、助教授を最後に、平成10年から現在地で矯正歯科臨床に専念している。
2011年4月14日(木)~4月21日(木)の1週間、愛知県歯科医師会から災害救護の依頼を受け、院長が被災地へ行ってきました。
診療車で、陸前高田市の下矢作コミュニティー、長部小学校、山田高校、大船渡小学校、吉里吉里小学校をまわり、多くの被災者に一般診療を行いました。大人も子供も口腔内の衛生状態は最悪な状態の方が多く、設備が不十分の中での診療であったため、どのようなトラブルに直面しても何かを代用するなど、とにかく完結する根性が必要でした。
避難所内には手書きの歯医者の訪問日を書いたポスターが貼ってあり、僅かながら我々歯科医の協力も被災者にとっては重要なんだと感じました。






・当医院は保険医療機関です。
・個人情報保護法を順守しています。
問診票、診療録、検査記録、処方せん等の「個人情報」は利用目的以外には使用しません。
■医療DX推進体制整備加算
当院は、医療DX推進の体制に関する事項および質の高い診療を実施するために十分な情報を取得し、及び活用して診療を行っています。
■歯科初診料の注1に規定する基準
歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた歯科医師が常勤し、職員に院内感染防止対策に係る院内研修等の実施をしています。
■歯科外来診療医療安全対策加算1
歯科外来診療における医療安全対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた歯科医師が常勤し、職員に医療安全対策に係る院内研修等の実施をしています。 また、緊急時には下記の医療機関と連携を取り、適切に対処を行える体制を整えています。自動体外式除細動器(AED)を常備しています。
■歯科外来診療感染対策加算1
歯科外来診療における診療感染対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた者が常勤し、院内感染防止に努めています。
■歯科治療時医療管理料
患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取る歯外在ことが出来ます。
■歯科訪問診療料の注15に規定する基準
在宅で療養している患者さんへの診療を行っています。
■歯科口腔リハビリテーション料2
顎関節症の患者さんに、顎関節治療用装置を製作し、指導や訓練を行っています。
■口腔粘膜処置
再発性アフタ性口内炎に対してレーザー照射による治療を行っています。
■歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算
歯科技工士との連携体制を整え、迅速かつ質の高い歯科技工の提供を行っています。
■歯科技工士連携加算2
歯科技工士と情報通信機器を用いた連携体制を整え、迅速かつ質の高い歯科技工の提供を行っています。
■CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。
■口腔粘膜血管腫凝固術
血管腫等の凝固が可能なレーザー機器を使用した手術を行っています。
■レーザー機器加算
口腔内の軟組織の切開、止血、凝固等が可能なものとして保険適用されている機器を使用した手術を行っています
■クラウンブリッジ維持管理料
装着した冠やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。
■歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
職員の賃金の改善を行い、働きやすい職場の環境づくりに努めています。